Articles
2020.04.14
ビームス、もう一人のすっごい設楽さん
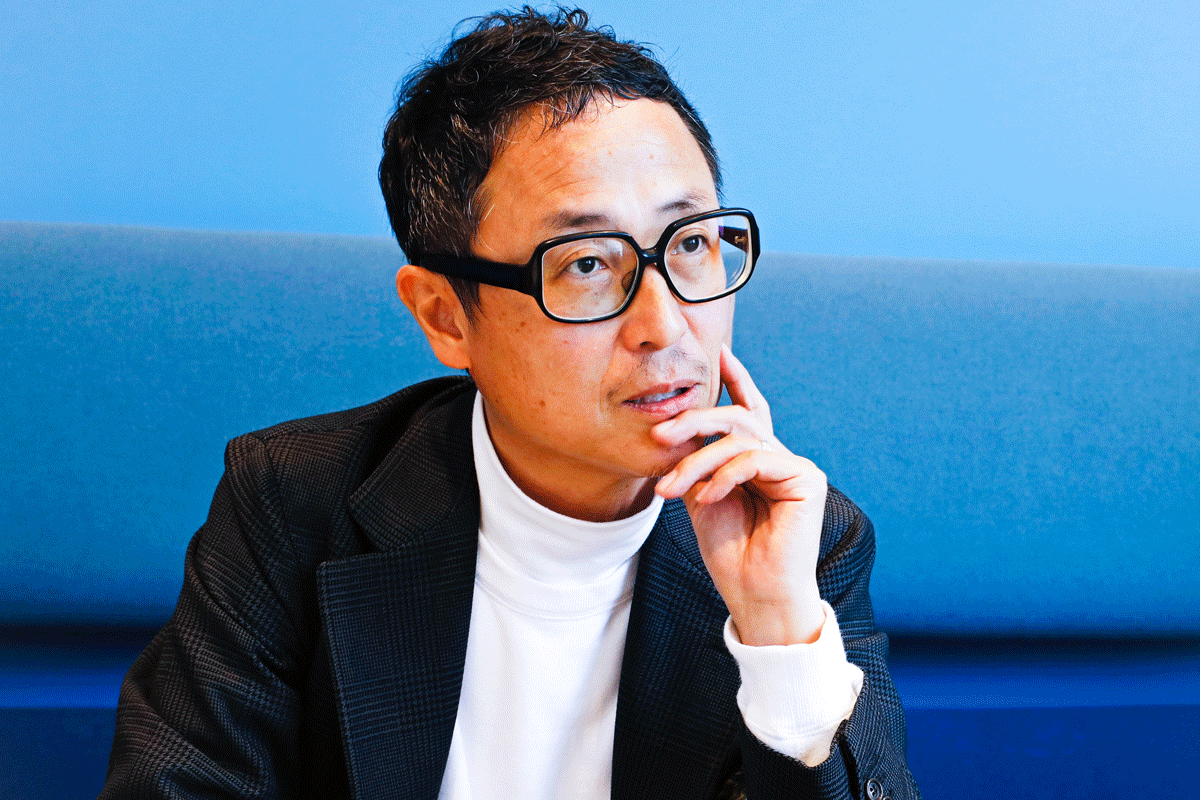
ビームス ライセンス事業課 副部長/ディレクター 設楽基夫氏インタビュー
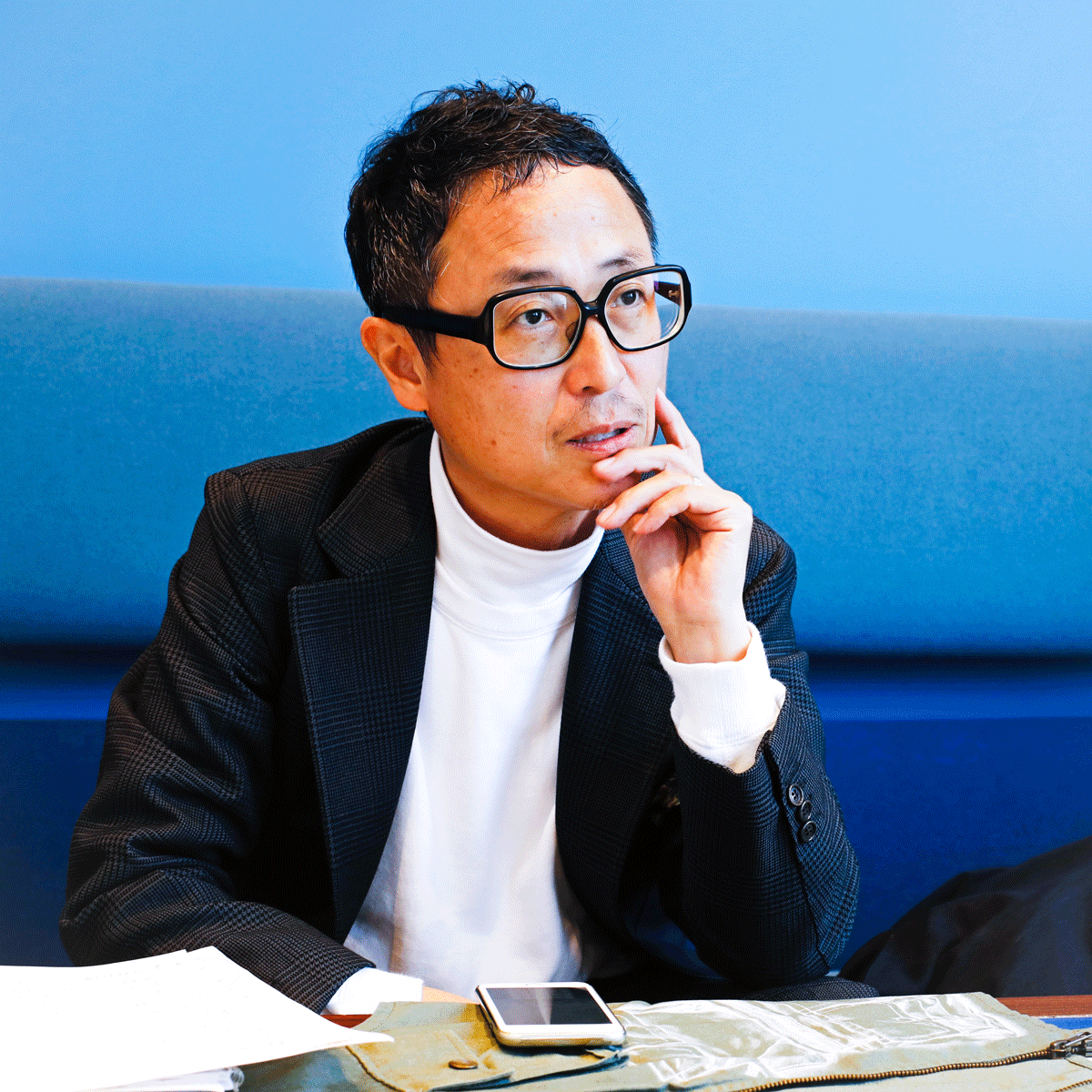
設楽基夫 Motoo Shitara
ビームス開発事業本部 ライセンス事業課 副部長/ディレクター。1964年山形県生まれ。25歳のときにビームスに入社。渋谷店勤務後、インターナショナルギャラリー ビームスのバイヤーを約15年務め、現職。趣味は映画鑑賞、買い物、お酒。最近は鳥を見るのが好き。
ビームスの社長はご存じ設楽 洋さんだけれど、ビームスにはもうひとりのすっごい設楽さんがいる。
15年にわたってインターナショナルギャラリー ビームスのバイヤーを務めた設楽基夫さんだ。
ちなみに基夫さん、設楽社長とは親戚でもなんでもないそうです。
どんなスタイルでご登場されるのかなぁと楽しみにしていたら、なんとなんとパニコのスーツ!
で、中は白のスウェット。
クラシックのセオリーを熟知した人が着崩すと、こうなるから面白い。
意外性を楽しむのが粋、みたいなのが洋服屋さんの中にあって、基夫さんのはまさにそれ。
さてさて、どんな話が聞けたでしょう?
―設楽さんがファッションに目覚めたきっかけから教えていただけますか?
設楽氏(以下敬称略) 小学校3年生か4年生だったかな。西城秀樹さんの真似から入っていきました。ジャニーズのフォーリーブスも大好きだったので、ラッパズボンというかフレアジーンズを穿いて、髪を伸ばしちゃったりして。それでグーンと視力が落ちました(笑)。その頃の写真を見ると全然似合ってなくて笑っちゃうんですけどね。グループサウンズはその後ジュリーにはまったり、最後はショーケンに夢中でした。
今に通じるファッションが好きになったのは、中学生になって『メンズクラブ』を買い始めてからです。くろすとしゆきさんが素人のスナップにコメントを寄せる「街のアイビー・リーガース」という企画が巻頭にあったんですけど、中学2年生のときにそこに載ったりもしました。
その後は『ポパイ』にどっぷりはまりましたね。スタイリストの御供英彦さんが手がけた古着の特集で、それまで断片的にしか知らなかった501XXとかビッグEとかファーストとかセカンドといった類のものが、きちんと体系的に説明されていたんです。そこから古着やインポートに傾倒し、山形から仙台まで電車で1時間以上かけて服を買いに行くようになりました。
大学で上京してすぐ、当時キラー通りにあったバセットウォーカーにアルバイトで入りました。バセットウォーカーは後に三代彰郎さんが入ってきてクラシコイタリア路線になるんですけど、当時はひと言でいうとレッドウイング屋さんだったんです。他にはアヴィレックスのボマージャケットやビッグマックのネルシャツなんかを扱っていました。渋谷パルコにも店があって、そっちでもたまに働いていたので、帰りによくビームス、キャンプス、ミウラ&サンズ、バックドロップ、スワンクあたりをハシゴしていました。ファイヤーストリートにレッドウッドがオープンしたのもその頃で、そこで働いていた友人から勧められるままにいろいろ買いまくりましたね。当時のものは今でも大切にとってあります。
―設楽さんのルーツはアメリカだったんですね!
設楽 アメリカには強く憧れていました。で、19歳のときに初めてサンフランシスコに旅行して。そしたらますます好きになってしまい、そのうち学校に行かなくなって留年しちゃって(笑)。それでも当時はそんなことまったく気にしていなくて、卒業後も就職はしませんでした。で、ほぼ毎日平日は草競馬場に出没していましたね。当たると、おっ、これで生きていける、みたいな(笑)。そのお金で服を買って渋谷のユーロスペースとかシネスイッチ銀座で映画を観る、みたいな優雅な生活を送っていましたね。一般的には無駄な時間に思えるでしょうが、当時に買った服や観た映画は、今の自分のベースを形成してくれた、とても貴重な時間だったのだと今は思っています。先日、Bunkamuraで、当時観た『バグダッド・カフェ』が上映していたので観にいったのですが、最初と最後以外、まったく憶えていませんでしたけどね(笑)。でも55歳にして、アメリカって最高じゃないか、自由だな、っていうのを再確認できました。『パリ、テキサス』や『蜘蛛女のキス』『ストレンジャー ザン パラダイス』『ミツバチのささやき』『エレファントマン』なんかもまた映画館で観てみたいですね。
―ビームスに入社したきっかけを教えていただけますか。
設楽 そんなことをしているうちに借金が溜まっていって、25歳のときに反省したんです。自分の性格が熱しやすくて冷めやすいのはわかっていたんですけど、じゃあ、何が出来るかなって考えたときに、ずっと飽きないのは洋服だなって気がつきまして(笑)。それでビームスに行って「入れてください!」とお願いして入社しました。それから30年が経ちましたが、ずっと続いているので、そのときの自分のインスピレーションは正しかったんでしょうね。ラッキーでした(笑)。
―他にもいろいろショップがあった中で、なぜビームスだったんですか?
設楽 一番好きな店だったからです。2番目に好きだったのがキャンプスでした。
当時、キャンプスの方が、ネイビーのブレザーにリーバイス501か505のブラックデニムを合わせ、トニーラマの黒いウエスタンブーツを履いていたんです。それがあまりに格好よくて衝撃を受けたんですよ。アメリカが大好きだったけれど、タンクトップにバンソンみたいなのは自分は華奢だし似合わないな、と。でもビームスには、セントジェームスにオールデンのローファーみたいなスタイルがあっていいな、と思ったんです。そっちのほうが自分らしく思えて、ビームスに入社を決めました。で、入ったら、楽しくて楽しくて。趣味の延長で仕事をしている感じで、子供が生まれた40歳過ぎまで仕事をしたという記憶がほとんどないですね(笑)。会社でも服の話ばかりしていました。
―最初はどちらの配属だったのでしょう?
設楽 渋谷店のB1Fにあったクロージングサロンです。重衣料の販売を担当しました。
元々、ブルックスブラザースとかJ.PRESS、ラルフ ローレンといった世界は通ってはいたんですが、自分の中でそれらはあくまでブランドものという認識で、重衣料という感覚がなかったんです。でもビームスに入社してそういった重衣料の世界に触れ、さらにサヴィル・ロウなどいろいろ知るようになり、奥の深いメンズクロージングの世界にどっぷり入っていきましたね。
―ビームスに入社して衝撃を受けたことはありますか?
設楽 みんな何て勝手で、服や女性や遊びなどの楽しいことしか考えていないんだろう、と思いましたね。『VOGUE』とか洋書が大好きで、そういうのを見ながら「やっぱりコレだよね」みたいに異様に盛り上がっていました。
―入社当時の設楽さんのスタイルはどんな感じでしたか?
設楽 1988年だったと思うんですけど、ジョルジオ アルマーニやジャンフランコ フェレがまだ流行っていて、それと並行して3つボタンスーツを着ている人もいる、みたいな感じでした。そんな中で僕がハマっていたのは3つボタンスタイルです。特に影響を受けたのがパリのマルセル ラサンスだったんですけど、その後SHIPSにいらした前淵さんがマルセル ラサンスのお店を代官山で始めたときは、ラサンスの店を日本でもやれちゃうんだって衝撃を受けましたね。その頃、FDG(エフデジェ)という言葉がでてきて、フランスの上品な着こなしを表現したものでお店でいうとエミスフェールとかオールドイングランドが代表的だったんですけど、提案する北半球の良いモノを混ぜて色を入れてみたり、きれいに論理的に着こなすスタイルが流行ったんです。自分にはそのFDGの着こなしがぴったりハマりました。BCBGとも言われていましたね。エミスフェールではオルテガのベストにリーバイス501、ウエスタンベルトをつけて、ジャコブソンと呼ばれていたオールデンの黒のカーフ黒のVチップをギュッと絞って合わせるみたいな提案もありました。やっぱりパリって違うんだなって、行ったことがなかったのですが、だから余計に憧れましたね。ゲンズブ―ルが流行っていたのでレペットを履いてみたりもしました。その後、ボサノヴァなどのブラジル音楽が流行りだして、CAYといったクラブにテーラードスーツを着て出かける流れが生まれ、クロージングがもてはやされるようになったんです。クラブに行くときは渋谷店のカジュアルなスタッフたちもスーツを着てきたりしてね。毎日のように夜中まで遊んで帰りに食べたかおたんラーメンは、今食べても美味しいと思える永遠の味です(笑)。青山トンネルを抜けたところにあったバー青山にはいろいろ面白い人が集まっていて、刺激的でよくそこへも通っていました。そんな生活をスノッブだと思っていました。

―ビームスで影響を受けた先輩はいらっしゃいますか?
設楽 ビームスは原宿と渋谷のお店で傾向がかなり違っていたんです。原宿は論理的で2枚目でスカしていて、渋谷は渋カジの終焉時代でやんちゃっていうのかな。例えばTシャツを着るなら体を鍛えようとか、ローファーを素足でカッコよく履くために海で日焼けしようとか。原宿店は「洋服屋とは」みたいな感じでピリッとしていて、南雲さんはその代表格でした。原宿はスーツを着るのもセオリーをきちんと守っていて、渋谷はどれくらい崩すのか、不協和音みたいなのが大好きで真面目に着ないことを追求していましたね。ちなみに無藤さん(現Brilla per il gustoディレクター)は渋谷でした。原宿店と渋谷店では文化が違いましたね。
―面白いなぁ、近場なのに店舗によってかなりカルチャーが違っていたんですね!
こういうのがビームスらしいんだ、と先輩から教わったり学んだことってありますか?
設楽 うーん、ラコステのポロシャツのワニを取って着ている人がいたんですけど、僕もマークとか入っているのがあまり好きでないんですね。皆、わりとそういう風潮だったんですよ。でも、マジ、取っちゃうんだ! そこまでやるんだ! というのを憶えています。あと当時クロージングのお店で普段はスーツでもセールのときは6ポケットのパンツとかカジュアルが許されていたんです。佐藤尊彦くん(現PRチーフディレクター)が、明日からセールだからラフな格好で来ていいよ、と後輩に言ったら、大きくラコステって入っているスウェットを着てきた人がいたんです。そうしたら佐藤くんが怒っちゃって「帰れ!」って言ってましたね。でも去年あたりビッグロゴブームがありましたよね? そのときに佐藤くんに、あの子、(取り入れるのが)早かったよね、って言ったら、苦笑いしていました(笑)
因みに怒られた人も、まだちゃんといます。
―誰だろう誰だろう、ククク、面白いなぁ! 他にも面白いエピソードありそうですね。
設楽 今もそうですが、アルバイトの人や若い人に逆影響を受けましたね。
ソロイストの宮下(貴裕さん)くんとか干場(義雅さん)くんがいた頃の渋谷は熱かった!二人のことは、毎日上から下まで見ていました。こんなふうに着るんだ、とかこの服の時はこんなヘアスタイルにするんだ、って。僕の若い頃はヘアスタイルをファッションで変えるってなかったんです。でも新世代の彼らにとっては、ファッションの一部にヘアスタイルもあるんですよね。ロン毛だった次の日にいきなりリーゼントで来たりするんですよ、干場くんは。びっくりしたけれど、見ているだけでこちらが嬉しくなる感じでした。あとは原宿のビームスFにいた登地勝志さんもストイックで驚かされました。ジェームズ・ボンドがとにかく大好きな方なんです。ある日、登地さんに飲みに誘ってもらったんですけど、「設楽くんは007の中で誰が好きかな?」と聞かれて「興味ないんです」と答えたら「そっかぁ」とすごい悲しそうな顔で言われました。で「高倉 健さんの映画は何が好きかな?」と聞かれて「1つも観たことないです」と答えたら、それでお開きになって二度と誘われませんでした(泣)。あのときは大人気なかったなぁと反省しています。
―登地さんの悲しそうな顔、想像できるなぁ。そして渋谷店勤務からインターナショナルギャラリー ビームスのバイヤーになられたんですね。
設楽 はい。そんなこんなしているうちに松山両三さんに呼ばれて一緒にヨーロッパへ出張に行くようになりました。初めてのときはたくさん自分の買い物をしすぎて、オマエは何しに出張に来たんだ、って怒られた記憶があります。展示会も面白かったんですけど、自分の買い物に対する熱量もすごかったんです。今でも変わらないですが。
―好きの延長で仕事をしているとそうやって夢中なってしまう(笑)。でもそれって、設楽社長が言っていた“努力は夢中に勝てない”っていうやつですね。それはいつ頃ですか?
設楽 確か28か29歳くらいだったと思います。当時は交代でいろいろな人が出張に連れていってもらっていたんです。インターナショナルギャラリー ビームスのバイヤーとして出張に行ったのは32歳のときでした。それから15年間バイヤーを務めました。その頃、皆によく話していたのは、単に洋服が好きっていうレベルじゃダメなんだ、そんな奴はゴマンといるし着倒れするくらいじゃないとダメなんだってこと。道楽を越えた者の集まりになるのがインターナショナルギャラリー ビームスなんだって。そういうパッションを語っていましたね。
バイヤーになった当初は昔から憧れていたこともあって、パリが大好きでした。マルセル ラサンスにかぶれていたので、ロンドンは伝統とパンクの街でもありながら、なんてプライドが高いんだろう、人々はちょっとお堅いんじゃないのと思いつつ、アンダーソン&シェパードが好きでした。いつか誂えたいっていう思いは今でもあります。
コンプレックスがあるんでしょうね、欧米に。でもそれを解消してくれたのがイタリアだったんです。イタリア人ってイギリスやアメリカが大好きじゃないですか。イギリス人よりもバランスがよくて、服も似合って、服を着るために生まれてきたような体型をしていて僕らから見たら全然似合っているのに、こんなにロンドンにコンプレックスをもっていて、人からどう見られるかを気にしているんだって。そこは日本人と同じなんだって。それを知ったらイタリア人のことが同志に思えてきてイタリアが大好きになりましたね。
時を同じくしてクラシコイタリアブームが来て、ルイジ ボレッリのシャツブームからイザイア、アットリーニ、そしてミラノのカラチェニやフィレンツェのリヴェラーノ&リヴェラーノ、ナポリのアントニオ パニコといったサルトリアに入っていきました。ナポリでロンドンハウス(ルビナッチ)を初めて訪れたときは、マリアーノ・ルビナッチさんのロンドンに対する純粋な想いに触れ、またその服装もロンドンの人より似合っていて、素晴らしいなぁとナポリが大好きになってしまいました。それと当時よかったのは、まだ通貨がリラでバールでエスプレッソを飲んでも70円くらいでしたから。お金持ちになった気分になれたんです。で、パリとロンドンに行くとうわ~、高いなってガックリするという(笑)。イタリアには僕らがイメージしていたクラシックなヨーロッパがいろいろな意味できちんと残っていたんですよね。それからイタリアに傾倒していきました。
―懐かしいですね! バイヤーとしての仕事はどうでした?
設楽 今思うと第1は自分の欲しいもの、第2は着道楽な人たちを満足させるという使命、第3に流れをしっかり見る、という考えで買い付けをしていました。もちろん数字も大切ですし、いわゆる売れるものを見つけるのは得意でした。今は分業ですけど当時はバイヤーといってもバイイングもするし、オリジナルの企画もするし、MDもするし、セールの値付けもするしで、なんでもやっていました。それだけでなく海外でオリジナルを作っていて、さまざまなことをやっていましたね。
オリジナル製品もクアトロッキというブランドを作ってイタリアで生産するようになって、カジュアルもドレスもイタリア一辺倒というのが10年くらい続きました。イザイア、アットリーニ、アントニオ パニコ、アンナ マトゥオッツォ、その他も本当にいろいろ着ました。特にアンナ マトゥオッツォには何度も通って、AMナポリという既製のラインも作ったりしましたね。イタリアのモノ作りしている人の情熱が大好きで、そういうのを見るとどっぷりハマってしまっていたんです。
で、クラシコイタリアが流行りだした中盤くらいにビームスFでも組下がノープリーツパンツのスーツを扱うようになって、ビームスFはイタリアンファッションの流れになってきたんです。
すると今度はインターナショナルギャラリー ビームスはよりニッチな方向へとシフトしていきました。コスチュームナショナルを着て、シルヴァノ マッツァの靴を履いているときもありましたね。僕はよいと思ったものはすごい好きになるんですが、ずっと好きなものはないんです。でも、また戻ったりして。ないものねだりというのでしょうか、常に違うことをしていたい、着たことがないものを着てみたいんです。
先日も透けている服を着ている人がいて、あ、こういうの着たことないな、と思って着てみたい!となったり。でも着た瞬間に飽きちゃったり、どうでもよくなっちゃうこともあります。嫌いになるわけではないんです。デニムをすごい大好きな人がデニムを穿いているのを見と、あ、僕はこの人ほど好きじゃないな、となって冷めてしまんですよね。
―そんな設楽さんがクラシックな服を着ると、とても新鮮でお洒落に見えます。何か秘訣はあるのでしょうか。何を着るにしても意識していることはありますか?
設楽 この時代とのバランスを大切にしています。自分の中のコレとコレを合わせるとこうなる、とか巡らせて考えるんです。出張の際によくロストバゲージしていたのですが、訪問先の社長さんたちが服を譲ってくるんです。僕の意に反するようなものだったりしても、合わせてみたりして、あ、これ結構いいじゃんみたいな(笑)。与えられたものを着こなせたときの感動は大きかったですね。そういった経験が今の僕を作っているのかもしれません。それと若い頃にはなかったことなんですが、自分で選んでいたら着なかったけれど、すすめられて着てみて、あ、確かにありだな、と新しい発見があるのも最近では楽しいです。
―ずっと愛用されている服はありますか?
設楽 10代の頃、レッドウッドで買った目無しのチャンピオンのスウェットです。
今でも最低年に1回はスーツの下に着ています。
―今日もスウェットの上にスーツですね。
設楽 はい、今日のスウェットはインターナショナルギャラリー ビームスのオリジナルで、昨年購入したものです。俺は王道だ、とかストイックになれないんです。なんか照れがあるのかもしれないですね。周りにストイックな人がたくさんいるせいか、自分はちょっとハズしたり抜いたりするようにしています。55歳の今もおしゃれの答えは見つかっていなくて分からない。明日という未来のほうが好きなんです。

これはVALORという、鴨志田(康人)さんがビームス時代に手掛けていたオリジナルブランドのシルクスカーフです。この頃は混沌としていてDCブランドもある、フェレやヒルトン、レダエリなどもある、ビスポークが出始めて、一方、山本耀司みたいな世界もある。そんなときにビームスを覗いていて一番格好いいなと思っていたのが、このVALORだったんです。基本的にはテイラードスタイルなんですが、ミックス感とか異国情緒を感じさせてくれる、そんなブランドでした。今も年に2,3回、着けています。スウェットにこういうスカーフを巻くといったスタイルは特に好きです。

クラスというブランドのデザイナーの堀切道之さんという方がいて、この方が僕の出会った人の中でもベスト3に入る服道楽なんです。その彼と一緒に仕事がしたくてたまらなかったんです。その堀切さんにインターナショナルギャラリー ビームスでミッチーホーリーという名前でベストを作ってもらったのがこちらのベスト(左)。ミッチーというのは堀切さんのあだ名です。
キャロルクリスチャンポエル(右)には衝撃を受けました。そのスーツが着たくて着たくて。これに当時パトリックコックスの靴を履いて青山とかに行って自分なりにスカしていました。スーツはもうないですが、このベストだけは残してあって、Tシャツの上に着たりしています。

これはエムズブラックの松下貴宏さんとコラボレーションさせていただいて、当時では画期的だったストレッチのリネンウールを使用したブレザーです。テーラードの世界ではストレッチのリネンウールなんてどこにもないんですけど、そういう素材をパリ中から探してきて一緒に作りました。これは今でも年に10回は袖を通しています。11~12年くらい前のものかな。

このUNTITTLEDのコーデュロイのスラウチジャケットはパリに行き始めた当時にバイイングしたものです。フランス製って素っ気なくで、ちょっと雑でどことなくアメリカ製に通じるものがある。どこまでも合理的でなんかいいな、と思いますね。
―アクセサリーなどは身につけますか?
設楽 ほとんどつけません。時計も最近はつけなくなりましたね。

―お持ちいただいたシャツはどちらのものですか?
設楽 ブルーストライプのものは一番大好きなアンナ マトゥオッツォでオーダーしたものです。イタリアのハンドメイドは、やはり好きです。ブルーのダブルカフスシャツはシャルベです。シャルベも大好きですね。ストイックなところがいい。パープルのストライプはリチャード ジェームス。マーク パウエルとかリチャード ジェームスといったニューテーラーブームの頃のリチャード ジェームスのものは今でも着ます。当時の上質な生地って、くたらないですね。

黒地にドットのスカーフはチェスター バリーの90年代のもので、今でも身につけています。

USA製のパナマジャックのスウェットはプリントに惹かれて購入しました。

メガネは少しインパクトのあるものを選びます。今日持ってきたのは、オリバーピープルズ、トム・フォード、トーマス・マイヤー、カトラー&グロス。

ベルナール ザンスのトラウザーズはアウトの2プリーツで、90年代から愛用しています。
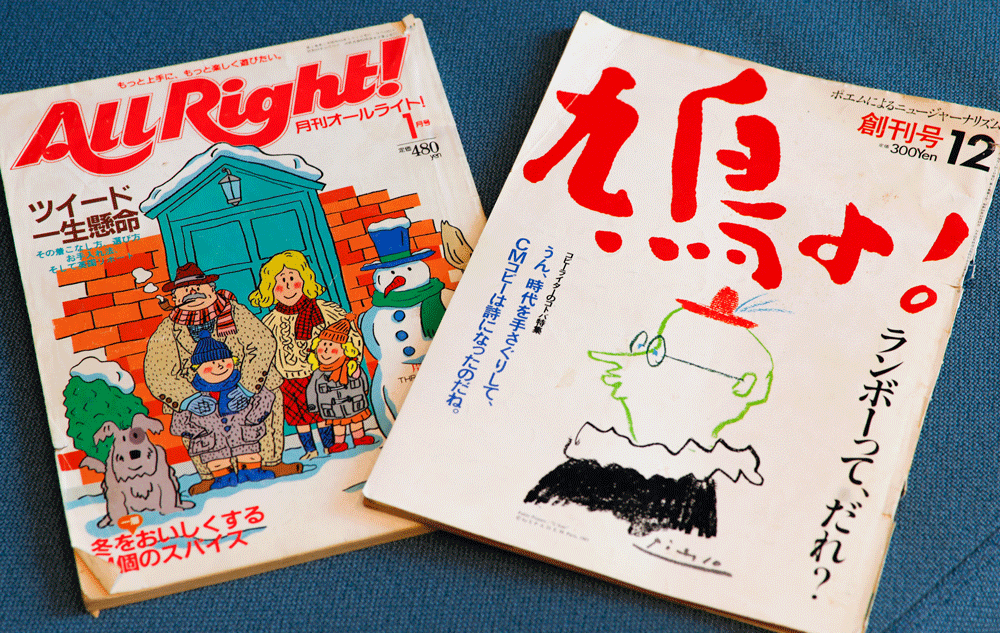
80年代の雑誌も好きです。マガジンハウスの文芸誌『鳩よ!』は昭和58年のもの。茨木のりこさんの詩集を読んで感動したことを思い出します。詩や落語が好きなんです。『AllRight』はすぐに休刊になってしまいましたが、好きな雑誌でした。ドクターマーチンの特集とかよかったなぁ。
―ところで設楽さんにとってのサルトリアルヒーローは誰ですか?
設楽 アントニオ・パニコさんですね。
ジャケットにはフラワー留めがあるものだ、というビームスのクロージングの常識があったので、あるとき「何故パニコの服にはフラワー留めがないんですか?」と質問したんです。そしたら「じゃあ、おまえは花を挿したことがあるのか?」と返ってきて。
えっ、それはないけれど、そういうものじゃないの?って思いつつ「ないです」と答えたんです。そしたら「だからないんだ」と。は~、なんて説得力があるんだ、それは素敵だな、って思いましたね。あんなにイギリス好きなのに囚われていない。誂え服の面白さって、キャッチボールするところにあると思うんです。僕はこう思っているけれど、と投げかけて、それに対して俺の服はそうじゃないんだ、と返ってくる。それに対して、また返す。そうやって作った服は捨てられないですよね。思い出も大事なフィルターです。
―なるほど。それとは別にご自身に影響を与えた方はいらっしゃいますか?
設楽 ミュージシャンだとマルコム・マクラーレン、デヴィッド・バロン、ジョン・レノン、マイケル・ジャクソン。
みんなローファーのイメージなんですけれど、僕にとってはスタジャンで、スタジャンってこういうものなんだ、と思わされました。あとはアクセル・ローズかな。
―アクセル・ローズですか!?
設楽 はい。裸ってファッションになるんだ、裸ってカッコいいな、と初めて思いましたね。なんでカッコいいのかというと、頭にバンダナを巻いているからかなぁ。
日本人ですと伊丹十三さん。洋服も似合うし、びっくりするような着こなしをされていて、本当にお洒落だったと思います。あとは加藤和彦さん、かまやつひろしさんです。GS時代のショーケンも好きだなぁ。何が素晴らしいって、タンクトップの着こなし方ですよね。映画『ベティーブルー』のような、ジャン・ユーグ・アングラードの着るタンクトップのカッコよさに近いんです。日本人でこんなにタンクトップをカッコよく着られる人がいるんだな、って思いましたね。
アーティストだとアンディ・ウォーホルとキース・ヘリング。
ファッション界だとジャンポール・ゴルチエ、ラルフローレン、ジョン・ガリアーノ、ヘルムートラング、ジルサンダー。
—バイヤーという仕事をしているとトレンドは気にしないといけない部分だと思うのですが、そこはどのように捉えていますか。
設楽 トレンドは意識します。展示会に行くと自ずとそういった話になりますしね。ひっぱられることもあります。でもそうじゃないな部分のほうが大きいので、自分がよいと思えるものを選びます。例えばどこかのバイヤーがこれを気に入って大量に買い付けていった、とか聞くと買わない、とかあります(笑)
―ヒヒヒ……。ちょっと天邪鬼的な要素がありますね! バイヤー時代に買い付けてヒットした商品はありますか?
設楽 最も金額的に売れたのはモンクレールです。15年くらい前の話になりますが、当時白のモンクレールってなかったんですね。なぜ、白がないのかというと、中のダウンが透けてしまうのでホワイトグースの選定が大変だったからなんです。でも、白シリーズを作ろうってことになり、入荷したらビームス史上に残る凄まじい長蛇の列を生む大ヒットとなりました。
パラブーツは作るモデルすべてがバカ売れして、調子に乗ってビットシューズを作って追加に次ぐ追加生産をしていたら、グ●チからクレームがきて作れなくなったことがあります。あとはオリジナルの3つボタンスーツは本当に売れました。
中村(達也さん)さんから、ビジネスマン向けスーツはビームスFでやるので違うスーツを作ってよ、とオーダーがあり、生まれた“エレガンス2Bスーツ”というのもありました。
スーツをお求めの方の中の99%はビジネスシーンでの需要。で、違うものとなるなら、自分が着たいもの、と思ってフロントのボタンを留めずに着られて、裾が少し跳ね上がっていてブーツやスニーカーにも合わせられるモデルを作ったんです。それは自分でももちろん気に入っていて、最近気分でまたヘビロテ中です。
―設楽さんはご自身が着ている服をどこの服なのかわからないように見せたい、と思われているような節があるように感じるのですが、いかがでしょう?
設楽 根底にありますね。例えば本当はすっごい気を遣って着ているんだけれど、そう思われたくない、とか。今日のパニコにスウェットとか(笑)。
―確かに、パニコにスウェット、初めて見ました(笑)。あと先ほどから映画の話が出てきますが、映画からファッションの影響を受けたことはありますか?
設楽 あまりないです。映画は純粋にストーリーを楽しんでいます。映画のファッションについて語っているのを聞くのは好きなんですが、でも結局スタイリストがついてやっているんでしょ?と冷めた目で見てしまう。嘘くさいことが苦手なんです。
―それ、わかります。最後に今日身につけているものを教えていただけますか?
設楽 スーツはアントニオ パニコで2002年に仕立てたものです。ハダースフィールドの生地だと思いますが、ミルやマーチャント名はわかりません。グレーとブルーの千鳥格子で、重厚感のある雰囲気とタッチが気に入っています。

クロコダイルのグルカサンダルはジャコメッティ。2年くらい前にシャークソールに替えて、なかなか評判がいいですね。

インナーに着たスウェットはインターナショナルギャラリー ビームスのオリジナル。
チーフは昔のドレイクス、メガネはヴィクター&ロルフです。
スーツにスウェットを合わせるような、ヌケ感のある着こなしが好きです。
入社当時から、毎日明日は何を着ようか、と考えるのが楽しくて、それは今も変わっていないですね。

Suit:Antonio Panico
Sweatshirt:International Gallery Beams
Shoes:F.lli Giacometti
Pocket Square:Drake’s
原稿 早島芳恵 撮影 藤田雄宏



